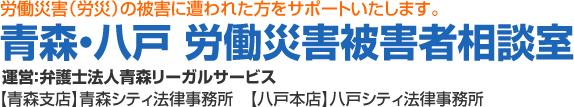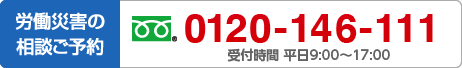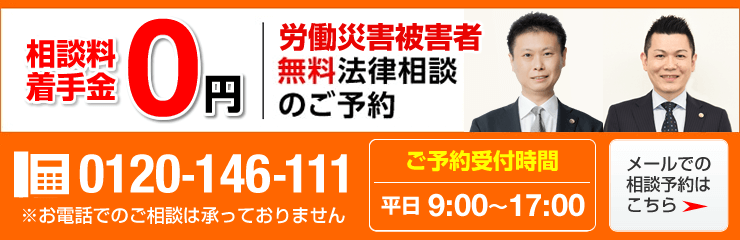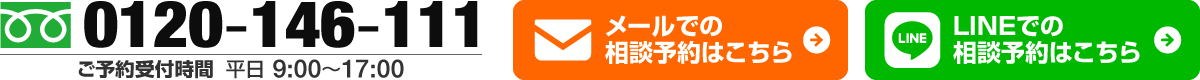1 労災隠しとは?

本来、会社は、労働災害等により労働者が死亡し、または休業した場合には、遅滞なく、労働基準監督署長に対して、労働者死傷病報告等をしなければなりません。
労災隠しとは、会社が労災事故の発生を隠すために、労働者死傷病報告を提出しないこと、または虚偽の内容を報告することにより、発生した労働災害の真実を隠すことをいいます。
2 よくある労災隠しのケース
会社が労災隠しをしようとする場合、以下のようなことを労働者に告げることが多いように見受けられます。
(1)「治療費はこっち(会社)が負担する」
治療費は会社が負担することを提案され、その代わりに労災申請をしないように言われます。
この場合、病院へ通院した際に業務中の負傷であるなどと真実を明かすことができず、別の負傷理由を告げることを指示されることもあります。
もっとも、このような指示に従ってしまった場合、後から労災保険の給付を受けたいと考えたとしても、労災事故を証明することが困難となってしまいかねません。
労災事故扱いとできない場合、労災保険給付を受けることができず、会社への損害賠償請求も困難となってしまいかねないため、その不利益は非常に大きいといえるでしょう。
(2)「うちは労災保険に加入していない」
一部の例外を除き、労災保険は、労働者を一人でも雇ったら加入しなければなりません。
(3)「正社員にしか労災保険は適用されない」
労災保険は、正社員のみならず、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートなどのすべての労働者に適用されます。
(4)「これは労災にならない」
労災になるか否かは判断する権利は、会社にはありません。
労災事故に遭った方は、このような会社の頓珍漢な言動を信用せずに対応する必要があることを留意しておくべきでしょう。
3 労災隠しは犯罪?罰則について
労災隠しは、犯罪です。
労災隠しをした場合、会社は、労働安全衛生法違反として50万円以下の罰金を受けることがあります。
労働者は、会社の労災隠しに加担したとしても、何らのメリットもありません。
むしろ、労災隠しに加担した場合、医療費を自分で負担しなければならないリスク、休職中の生活費の補填を受けることができないといったリスクを負うこととなるため、デメリットしかありません。
また、労働基準法上、業務上の怪我・病気を療養するために休業する期間とその後30日間は解雇することができないと定められていますが、労災隠しがなされ、労災事故の証明ができなくなった場合、会社から、不当に解雇されるリスクまで負うこととなりかねません。
そのため、労働者としては、労災隠しに対しては毅然とした対応を取る必要があります。
4 会社に労災隠しをされた場合の労働者の対応
会社に労災隠しをされた場合、まずは労働者自身で対応していく必要があります。
以下のように、労災の手続は、会社ではなくとも行うことができますので、参考にしていただければと思います。
(1)治療について
労災事故による怪我の治療は、できる限り、労災保険指定病院で行うことをお勧めいたします。
労災保険指定病院であれば治療費を負担する必要はないので、生活を圧迫することもありません。
労災保険指定病院は、インターネット検索で簡単に調べることができるので、お住まいの近くの病院を探してみていただければと存じます。
お住まいの近くに労災保険指定病院がない場合は、労災保険指定病院以外の医療機関を受診しても問題ありません。
この場合、一度窓口で立て替えて治療費を支払う必要がありますが、後日、労働基準監督署に申請することで治療費が支給されます。
なお、労災の傷病の治療には、健康保険を使うことができません。
そのため、健康保険を使用して病院を受診している場合は、労災保険に切り替える必要があります。
この際、労災保険への切り替えができない病院もありますので、注意する必要があります。
労災保険への切り替えができない場合、自身の加入する健康保険組合に、今回の負傷が労災である旨申し出てください。
健康保険組合の手続に従って、医療費の返納を行い、その後、労働基準監督署へ、支払った医療費の請求をすることができます。
(2)労働基準監督署への相談
会社が労災申請を行わない場合は、労働基準監督署へ相談すべきでしょう。
労働基準監督署は、労災隠しを厳しく取り締まっているので、躊躇せず、連絡してください。
また、労災申請にあたって、通常は、申請書に会社の押印が必要となりますが、事前に会社が労災申請を行ってくれない旨の事情を労働基準監督署に書面で提出することにより、会社の押印がなくとも、労災申請を受理してもらえます。
5 労災隠しの被害に関するお悩みは当事務所にご相談ください
労災事故の被害にあった労働者は、労災保険等により、適切に治療を受けるとともに、補償を受ける権利があります。
労災隠しは犯罪であり、労働者のこのような権利の実現を阻害しかねないものであるため、決して許されるべきものではありません。
また、会社は、職場における労働者の安全と健康を確保する義務を負っています。
発生した労災事故が、会社の安全配慮義務違反によって生じたものであれば、会社に対する損害賠償請求も考える必要があります。
労災隠しが行われている場合、労災隠しに関する労働基準監督署に対する告発に加え、労災保険の給付に関する手続や、会社に対する損害賠償請求について、適切に対応していく必要があります。
ご自身に不利益が生じないためにも、会社の労災隠しに関してお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談いただければと存じます。
労働災害の被害に遭われた方はこちらもご覧下さい
●労働災害の被害に遭われた方へ
●労災保険による補償と損害賠償請求について~被害者やご家族が知らないと損をする事実~
●労働災害を弁護士に相談した方がよい3つの理由
●労働災害の被害に遭った時に頼りになる弁護士の選び方~弁護士のここで差が付く~
●弁護士に相談するタイミング
●弁護士に依頼した方がよいケース
●労災保険の申請でお困りの方へ
●労災隠しとは?会社が対応してくれない場合の対応方法について弁護士が解説
●労災保険の後遺障害認定手続サポート~適正な障害等級の認定を受けるために~